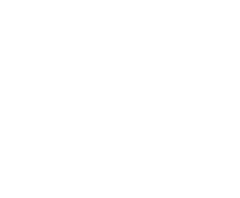【Twitter】正解発表!『ワクワクお寿司クイズ』
2022年11月1日(火)~ 11月14日(月)の期間で開催したTwitter企画『ワクワクお寿司クイズ』
たくさんのご参加ありがとうございます(^^)
今回は寿司の日にちなんで豆知識問題が多かったので、前回の根室クイズより簡単だったのでは・・?
花まるでお寿司を食べるときにフフッと思い出してもらえたら嬉しいです。
さて、それでは早速【正 解 発 表】にいきましょう。
1.【○×問題】すしが日本に伝わったのは江戸時代である。○か×か!
正解は「×」でしたー。
江戸時代っぽいですが、実は「すし」が日本に伝わったのは奈良時代と言われています。
初期の日本の「すし」は魚介類を塩と米で漬け込んで発酵させた、保存食の一種。いわゆる「熟れずし(なれずし)」で、滋賀県の名産「ふなずし」がその典型だそうです。
私たちがイメージする握り寿司にグっと近づいたのはそう、江戸時代です。

2.【選択問題】「シャリ」の語源はどれでしょうか?
正解は「お釈迦様の骨」でしたー。
なんと、まさかの骨とはヽ(; ゚д゚)ノ
シャリというのは「舎利」と書き、仏教用語で火葬されたお釈迦様の骨のこと(仏舎利)をさします。
仏舎利は大変尊いものとされていて、細かく砕かれた骨の形と白さが、米粒に似ていることから例えられたいう説があります。
他にもサンスクリット語で米粒のことを「sari(シャリ)」と呼んでおり、仏教を通じて日本にも伝わって、日本でも白飯をシャリと呼ぶようになった説もあるのだとか。

3.【記述問題】むかーしむかしの寿司屋さんは○○○が汚れているのが繁盛している証だったとか。○○○とは一体何でしょう?
正解は「のれん」でしたー。
昔の寿司屋では、最後に湯呑みに残ったお茶で寿司を持っていた手を洗い流し、のれんで手を拭いて店を出て行ったとか。
そんなエピソードから、のれんが汚れている店ほど「何度も手を拭かれていた証」=「美味しい店」とされていたようです。ふむふむ。

4.【選択問題】寿司ネタに欠かせない「トロ」、どうして「トロ」というでしょうか?
正解は「トロッとした食感」でしたー。
今でこそ人気のトロですが、昔は赤身は食べてもトロは食べずに捨てられていた⁉ 脂身は傷みが早かったからですね。
それが大正時代、吉野鮨の常連さんが人気のなかった脂身の部位を「口の中でトロける!」「口にいれるとトロッとする!」ことからトロと名付ける提案をしたんだとか。するとその響きが他のお客さんの食欲をそそり、徐々に好んで食べる人が増えて…。現在ではトロは赤身の2倍以上の値段がつく、寿司には欠かせない人気のネタになりました。

5.【選択問題】これから寒くなる季節にピッタリの汁物。さて、花まるで人気の「鰍汁(○○○じる)」は何と読むでしょうか?
正解は「かじか」でしたー。
別名"なべこわし"(鍋にすると美味しすぎて取り合いになり、箸の勢いで鍋が壊れてしまう)なんて呼ばれるかじか。その名前からも分かるとおり秋から冬にかけてが旬なので、冬の花まるでも必ず登場するのがかじか汁です。今年の冬もぜひお楽しみください♫

というわけで、全問正解されたでしょうか?
改めて、Twitter企画『ワクワクお寿司クイズ』にご参加いただきありがとうございました。
最後に…
今回のクイズで全問正解された方の中から抽選で10名様に「花まるお食事券」をプレゼントします♪
今回のクイズで全問正解された方の中から抽選で10名様に「花まるお食事券」をプレゼントします♪
当選されたお客様にはTwitterのDMにてご案内しますので、ぜひご確認ください。